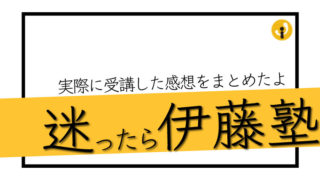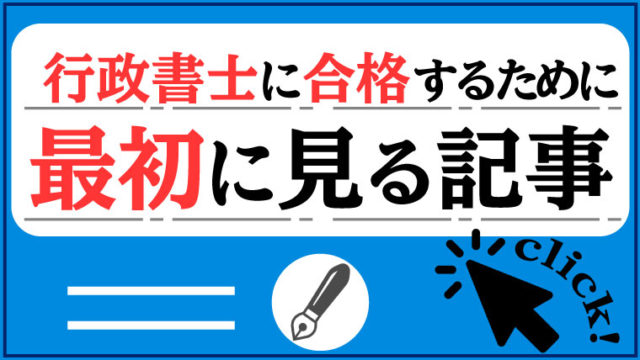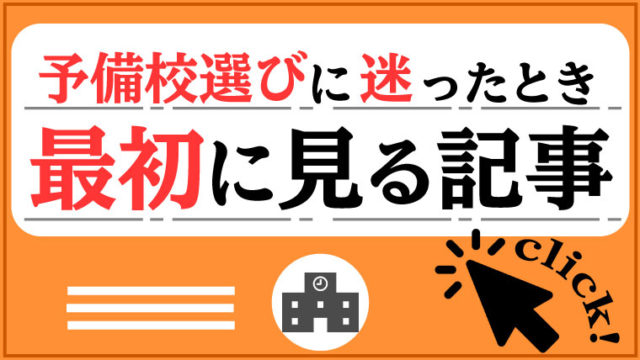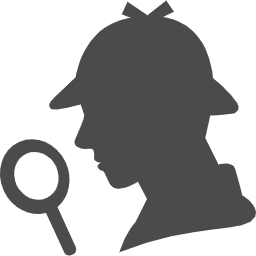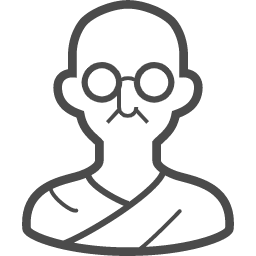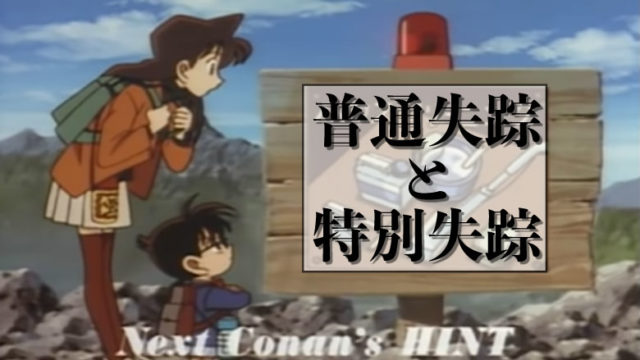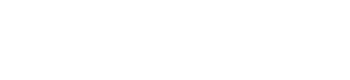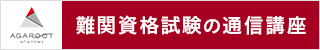最終更新日:2021年4月2日
この記事を書いているのは2021年4月1日。
四月一日と書いて「わたぬき」さんという苗字が存在するそうです。
それはさておき今回のテーマは【通謀虚偽表示】!
まさにエイプリルフールの今日にピッタリ!
特にみんな混乱するのが「通謀虚偽表示の類推適用」ですよね。
Twitterを引用させていただきます。
「通謀していないのに適用された」ではなく、通謀虚偽表示の規定を【類推適用】したのです。直接適用と類推適用は意味が大きく異なります。
「直接適用できないから強引に解釈して無理矢理当てはめた」という前提で判旨を読んでみると意味がわかると思いますよ!— 178点不合格を経験した男 (@gyo_sho_pass) March 31, 2021
このままでは意味がわかりにくいので、わかりやすく解説します!
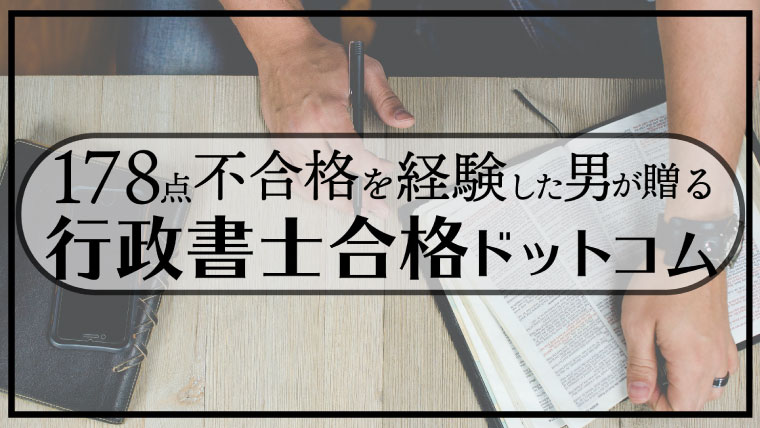
通謀虚偽表示をわかりやすく!
まず通謀虚偽表示の原則について先に整理します。
根拠になるのが民法第94条。短い条文なので声に出して読んでみてね。
第94条
① 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
② 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法第94条1項
民法はひとびとを守るための法律ですが、守る価値のないひとは守りません。
1項の内容はこれだけです。
AさんとBさんというふたりしか登場しません。

条文のとおりなので簡単ですね。
ひとまず【通謀虚偽表示は原則無効】と覚えてしまいましょう!
民法第94条2項
混乱の原因は2項にあります。
2項の内容には第三者であるCさんが登場します。
こんなストーリーです。

- AB間で通謀虚偽表示をした
- CさんがBさんの所有物だと信じてBさんから土地を買った
- その後AB側が1項の規定を根拠にCさんとの売買は無効だと主張した
この中で一番守りたいひとを考えてみてください。
おそらくあなたの考えは民法の考えと一致しているはず。
そうです。守るべきはCさんです。
なぜかというと、【CさんはBさんから土地を買いたかっただけ】で、通謀虚偽表示の話なんてまったく知らなかったからです。
Cさんからしてみれば、取引が成立した後になって、相手方から通謀虚偽表示を根拠に無効と主張してこられたらたまったものではありません。
いわゆる「取引の安全性を守る」という考え方。
1項の内容だけではCさんを守ることができないので、2項で善意の第三者Cさんを守るためのルールを規定したというわけです。
第94条の構成が理解できたでしょうか。
通謀虚偽表示の判断基準は3つ!
行政書士試験で深く問われることはないですが、通謀虚偽表示のキーワードを3つ紹介しておきます。
- 虚偽の外観
- 帰責性
- 第三者の信頼
深入りする必要はありませんので、少しだけ解説しますね。
虚偽の外観
言葉のとおりです。
不動産が問題になるケースがほとんどですので、ここでは「登記」と考えます。
AB間で通謀虚偽表示を行い、AさんがBさんに土地を売ったという事例で考えると
【登記簿で確認したところ「Bさん」が所有権者になっている】
この場合、誰もがBさんの所有物だと考えますよね。
権利外観法理と呼ばれたりしますが、難しく考えなくて大丈夫。
帰責性
イメージは「積極的に虚偽の外観を作り出したどうか」です。
上の例のように、取引をしていないのに登記を移すのは明らかに帰責性ありです。
「実際には取引をしていなかった」と主張してもとおりません。
第三者の信頼
イメージとしては「Cさんが信頼していたかどうか」です。
【善意の第三者】ですので、信頼して取引をしたと考えられます。
要件までは深く問われないので、流してもらって大丈夫です。
ここから通謀虚偽表示の類推適用についてわかりやすく解説します。
みんなが混乱する通謀虚偽表示の類推適用!
ここまでで
- 1項:通謀虚偽表示は原則無効
- 2項:善意の第三者を守るための法律構成
と理解がすすんできました。
判例を1つだけ覚えてね!
行政書士試験で得点するためにもうひとつだけ重要な知識をお伝えします。
通謀虚偽表示の類推適用です。
このテーマで勉強する判例はひとつだけです!
オンリーワンです!これだけ覚えていれば問題なし!
とにかく、あれこれ考える必要は皆無です!
めっちゃ出題される判例
- 不動産の所有者であるXから当該不動産の賃貸に係る事務や他の土地の所有権移転登記手続を任せられていた甲が,Xから交付を受けた当該不動産の登記済証,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき甲への不実の所有権移転登記を了した場合において,Xが,合理的な理由なく上記登記済証を数か月間にわたって甲に預けたままにし,甲の言うままに上記印鑑登録証明書を交付した上,甲がXの面前で登記申請書にXの実印を押捺したのにその内容を確認したり使途を問いただしたりすることなく漫然とこれを見ていたなど判示の事情の下では,Xには,不実の所有権移転登記がされたことについて自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があり,Xは,民法94条2項,110条の類推適用により,甲から当該不動産を買い受けた善意無過失のYに対し,甲が当該不動産の所有権を取得していないことを主張することができない。
※判旨の赤文字部分とマーカー部分だけは読んでね。

裁判所、困惑!!
Xさんいい加減なことしすぎ!Yさんを守ってあげるべき!
あなたもそのように感じられたのではないでしょうか?
Yさんを守るためには法律の根拠が必要です。
しかし残念、民法にはYさんを守ってあげられそうな条文が見当たりません。
- Xさんは注意すれば防げたのに何もしていない
- XさんよりもYさんを守るべき事例
- Yさんを守るために法律をどう解釈するか
そこで裁判所は裏技的解釈でYさんを守ることにしました。
発動!通謀虚偽表示の類推適用!!
Xさん甲さんは積極的に通謀虚偽表示をしたわけではありません。
なんせXさんは取引自体に無頓着で、甲さんに土地を任せっぱなし。
これでは通謀虚偽表示を直接適用するのは不可能。
じゃあ類推適用って形でなんとかするぜ!
これがこの有名な判例のストーリーです。
「通謀虚偽表示と同視しうる」と表現されるやつです。
理解できましたでしょうか。
通謀虚偽表示に学ぶ法律解釈
「結論ありき」という言葉があります。
その名のとおり、結論が先にあるものの根拠を探すという状況。
法律の世界でも結論ありきと呼ばれる判例は多くありますが、受験生レベルでは判断しにくいと思います。
テキストでは「誰を守るべき」とか「Yさんがかわいそうですね」とはなかなか書けませんし、「結論ありきの判例だ」と書くのも難しいのです。
ブログなので今回の記事のような表現ができますが、本の出版となるとそうはいかないはず。
市販のテキストがわかりにくい理由ってそこにあるんですよね。
法律初学者からすると混乱するのは当たり前です。
今後もできる限りわかりやすいブログを作り上げていきますので、よかったらSNSでシェアしてもらえると嬉しいです。